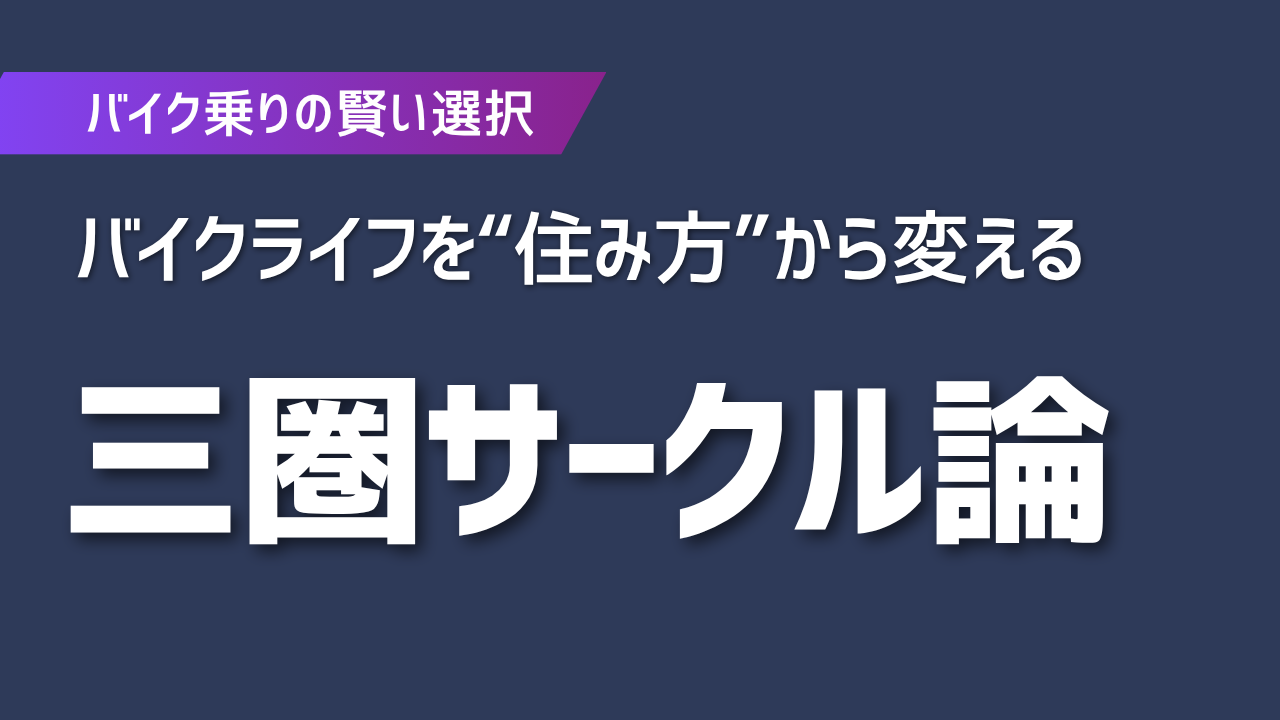住む場所を選ぶ、もう一つの基準
家賃、通勤時間、買い物の便利さ。多くの人が住む場所を決めるとき、こういった生活の合理性で判断する。
でも、バイクと生きる人にとって、本当に大事なのはそこじゃない。
僕にとって住む場所とは、どこを走れるかで決まる。
もっと言えば、“どこを起点に人生を走るか”。
その考えを形にしたのが、僕が提唱する「三圏サークル理論」だ。
三圏サークル理論とは?
この理論は、自分の暮らしを中心に半径50km・100km・150kmの3つの円を引いて、
それぞれの「走域」を意識して住む場所を設計する考え方。
僕は、この円で描かれる個人の走域を「RIDE FIELD(ライドフィールド)」と呼んでいる。
この3つのサークルには、それぞれ異なる役割がある。
50km圏:ちょい乗り圏(=日常の呼吸)
ふと「少し走りたいな」と思ったときに、往復2時間以内で行ける範囲。
ここに、海や山、気持ちのいいワインディングがあると、心が整う。
“生活とバイクが地続き”になるかは、ここがすべてと言ってもよい。
100km圏:日帰りツーリング圏(=心のリセット)
休みの日など1日フルに時間を使える日に、走る範囲。
日常から離れてリフレッシュする、“自分の癒しの場所”。
風景に没入し、気持ちを整理する。
そんな”精神のベストプレイス”がここにあると、人生はすごく生きやすくなる。
150km以上:非日常圏(=知らない世界へ)
1泊やロングツーリングで走るエリア。
ここでは、その土地に根付いた文化、景色、食、そして“非日常”が待っている。
この距離にどんな多様性があるかで、バイク旅の豊かさが大きく変わる。
重要な評価軸
三圏サークル理論でRIDE FIELDを設計するときに重要なのは、距離だけじゃなく「質」だ。
特に以下の要素が効いてくる。
- 激しい渋滞や二輪走行規制の有無(例:東京や関西圏)
- 1年中走れる気候か(冬季閉鎖の有無)
- 海・山・川のバリエーションと密度
- 食・文化・温泉など“走る意味”のある目的地
この視点で見たとき、僕が最終的に選んだのが福岡だった。
僕のRIDE FIELD:福岡の圧倒的強み
- 50km圏:糸島、志賀島、八女、三瀬、唐津
- 100km圏:阿蘇、日田、湯布院、平戸、雲仙、下関
- 150km以上:霧島、桜島、高千穂、日南、角島
信号が少なく、道が快適で、冬でも走れる。
福岡から広がる三圏サークルには、日常から冒険まで走るためのすべてが詰まっている。
あなたも、自分の三圏サークルを描いてみてほしい
地図を開いて、自宅を中心に三つの円を引いてみてほしい。
その中に、あなたの“走りたい場所”はあるだろうか?
気持ちをリセットできる場所から、生涯のベストプレイスまで。そのバランスはどうだろうか?
僕はその問いに正直になって、住む場所を変えた。
そして今、2台の大型バイクを所有する福岡で、”走るように暮らす”日々を生きている。
終わりに:旅と暮らしの境界をなくすために
バイクは、”行き先を決める自由”そのものだ。
でも、その自由をもっと深く使うなら──
「どこを走るか」ではなく、「どこから走るか」まで考えて選ぶべきだ。
それが、三圏サークル理論の思想であり、RIDE FIELDという世界観だ。
次回は、この理論を使って、全国の拠点候補を比較してみたい。
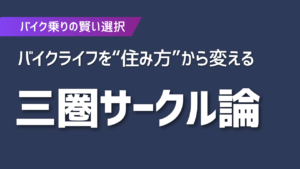
──あなたの暮らしが、少しでも“走るような毎日”に近づきますように。