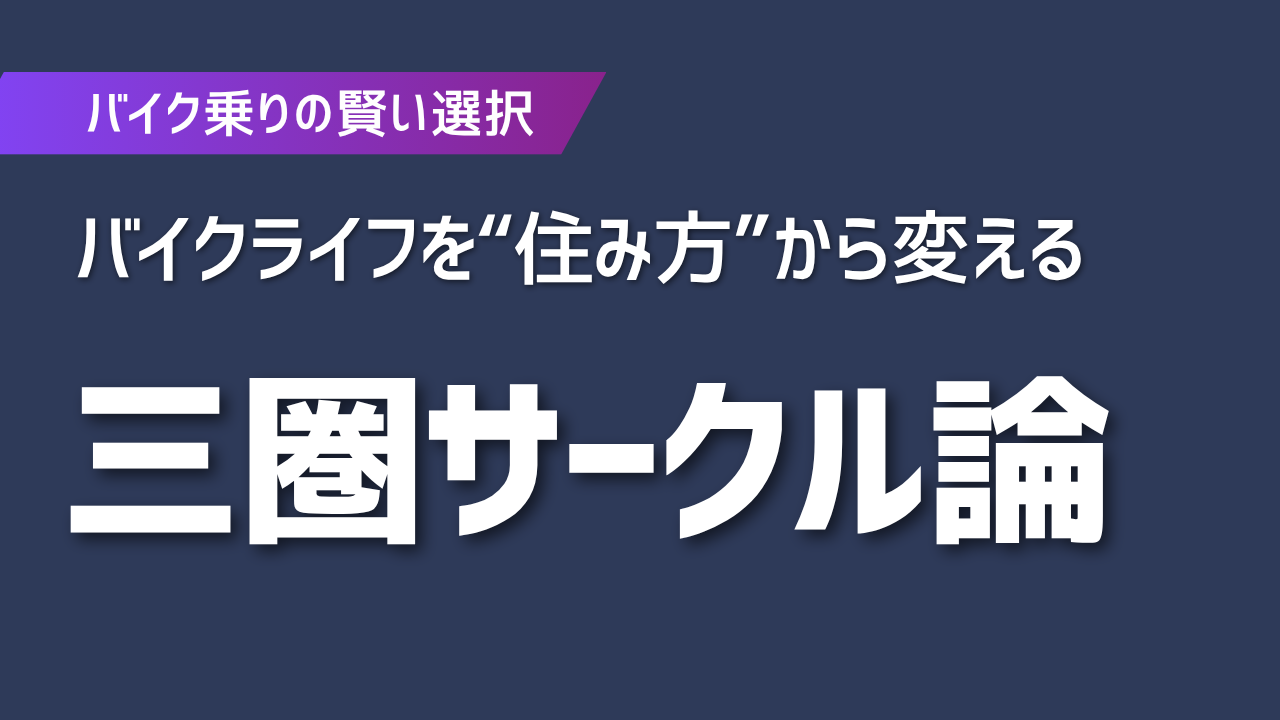この記事は、前回紹介した「三圏サークル理論」の続編です。
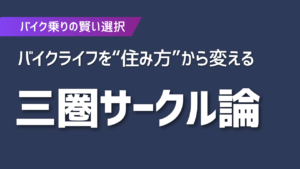
「どこを起点に走るか」は、ライダーにとって人生の選択を左右する。
走りたい場所を追い求めてきた僕にとって、それは旅の話ではなく、暮らしの話になった。
前回紹介した「三圏サークル理論」では、生活の中心から半径50km・100km・150kmを描き、
それぞれの“走域”でどんな景色に出会えるかを重視する考え方を提案した。
今回はその理論を使って、全国の移住候補地を本気で比較してみる。
ポイントはひとつ──
「走るように暮らす」を、本当に実践できる場所はどこか?
比較対象はこの5拠点
| 拠点 | 特徴 |
|---|---|
| 福岡 | バイクと生活が地続きになる都市 |
| 長野 | 山岳ツーリングの聖地、でも冬は長い |
| 静岡 | 富士を走る絶景圏、ただし雨多し |
| 大阪 | 走るにはやや辛い、都市の渋滞 |
| 東京 | 情報豊富だが、窮屈で不自由な街 |
総合評価チャート
| 都市圏 | 走行環境 | 景観多様性 | 渋滞・規制 | 都市機能 | 総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★★★★★ |
| 長野 | ◎ | ◎ | △ | △ | ★★★☆☆ |
| 静岡 | ○ | ◎ | ○ | △ | ★★★☆☆ |
| 大阪 | △ | ○ | △ | ◎ | ★★☆☆☆ |
| 東京 | △ | ○ | × | ◎ | ★☆☆☆☆ |
各拠点の詳細分析とレビュー
福岡|走る場所に“住む”という感覚
走行環境:◎ / 景観多様性:◎ / 渋滞・規制:◎ / 都市機能:◎
通年走行:◎ / 出発からの快適性:◎ / 100km圏の密度:◎ / 文化・食・温泉:◎
福岡は、とにかく“すぐ走り始められる”のが最大の魅力。
市内からわずか15分で海沿いの道にアクセスでき、30分あれば山道のワインディングを楽しめる。
糸島や志賀島、三瀬峠など、生活圏にツーリングスポットが溶け込んでいるのは他にない強みだ。
日帰り圏(100km)には阿蘇、平戸、湯布院…と、日本トップクラスの密度で多様な風景が詰まっている。
特に、日本最高峰の絶景ロードを誇る阿蘇・九重エリアにアクセスが容易な点は、大きな強みだ。
しかも、冬でもほぼ通年走れる温暖な気候。
通勤も旅も、バイク一台で完結する。
さらに、都市機能(地下鉄・空港・大型病院・商業施設など)も全て近接している。
以上から、“走るように暮らす”を最も自然に実現できる都市と断言できる。
長野|天空の道と四季のドラマ。でも暮らしには覚悟が要る
走行環境:◎ / 景観多様性:◎ / 渋滞・規制:○ / 都市機能:△
通年走行:× / 出発からの快適性:◎ / 100km圏の密度:◎ / 文化・食・温泉:◎
ビーナスライン、志賀草津、蓼科──名だたる天空ロードが走り放題。
まさに「走ること」そのものを目的にできる聖地が長野。
走り出してすぐに山岳ワインディング、しかも交通量も少なく快適そのもの。
しかし、冬は路面凍結・積雪で4〜5ヶ月ほぼ走行不能で、長い冬眠を強いられる。
この一点で、バイク生活にとっては大きな制限となる。
都市機能も限られ、職種やライフスタイルにかなりの“地元適応力”が求められる。
自然に全振りできる人向けの、上級者RIDE FIELDと言える。
静岡|富士の麓で絶景を浴びる日々。ただし晴天は約束されない
走行環境:○ / 景観多様性:◎ / 渋滞・規制:○ / 都市機能:△
通年走行:△ / 出発からの快適性:○ / 100km圏の密度:○ / 文化・食・温泉:○
富士山と太平洋を背景に、海岸線と山岳ルートを両立できる稀有な地。
伊豆スカイラインや富士五湖など、“映えるルート”の宝庫だ。
ただし降水量が全国でもトップクラスに多く、路面状況が不安定。
バイク乗りには「予報との戦い」が常に付きまとう。
都市機能も東西に分散し、移動がやや非効率。
ツーリング地としてのポテンシャルは高いが、住むとなると意外に難しさが残るエリア。
大阪|選択肢は広い。でも日常で乗るにはハードモード
走行環境:△ / 景観多様性:○ / 渋滞・規制:△ / 都市機能:◎
通年走行:◎ / 出発からの快適性:△ / 100km圏の密度:◎ / 文化・食・温泉:○
さすが大都市で、ショップ・仲間・情報・イベントには困らない。
そして、100km圏には和歌山・淡路島・奈良など豊富なルートが揃っている。
問題は、都市を出るまでに30〜60分のストレスを伴うこと。
信号が多く、走る前に心が折れやすい。
都市機能は抜群だが、それがバイクにとっては“足かせ”にもなる。
郊外に住んで逃げ場を作れるかどうかが鍵。
また、関西のワインディングは二輪通行規制が多く、意外と走りがパターン化しがち。
東京|便利だけど、バイクが“窮屈になる”街
走行環境:△ / 景観多様性:○ / 渋滞・規制:× / 都市機能:◎
通年走行:○ / 出発からの快適性:× / 100km圏の密度:○ / 文化・食・温泉:○
情報・人・モノ・イベント──すべてが集中している日本の中心。
けれど、ことバイクに関しては制約の多さが自由を奪う。
通行規制、駐車禁止、首都高二人乗り不可、そして地獄のような渋滞。
バイクは“自由の象徴”であるはずなのに、ここではそれが機能しない。
100km圏に行けば素晴らしい場所も多い。
しかし、そこにたどり着くまでが試練。
慢性的な渋滞のせいで、ツーリングの行き帰りに非常にストレスフルな時間が生じる。
もはや、渋滞するために走っているのではないかとすら思えてくる。
東京で10年暮らした僕が断言する。
走ることが目的なら、東京は選ばない方がいい。
最終評価まとめ:RIDE FIELDの理想形は、やっぱり福岡
こうした各拠点の分析・評価を通して見えてきたのは、
福岡の“あらゆるバランスの良さ”が飛び抜けているという事実。
- 出発してすぐに走れる
- 年中いつでも走れる
- 都市と自然の距離が異常に近い
- 美味しいごはんも温泉もすぐそこにある
- 隣県にある国内最高峰の絶景ロードにアクセス容易
「走るように暮らす」を本当に実現できるのは福岡しかない。
結論|RIDE FIELDを描くなら、福岡から始めよう
バイクは、自由に行き先を決められる乗り物。
でも、その自由を最大限に活かすには、「どこから走るか」まで意識することが大事だ。
福岡を拠点に三圏サークルを描いたとき、
その円の中に、「走りたい風景」「暮らしが息づく文化」「癒される時間」が全部あった。
その感覚が、“走るように暮らす”というライフスタイルを支えてくれる。
東京を離れ、福岡に拠点を移して、本当に良かったと思っている。
僕はいま“走るように暮らす”という言葉を、ただの理想ではなく、確かな日常として生きている。